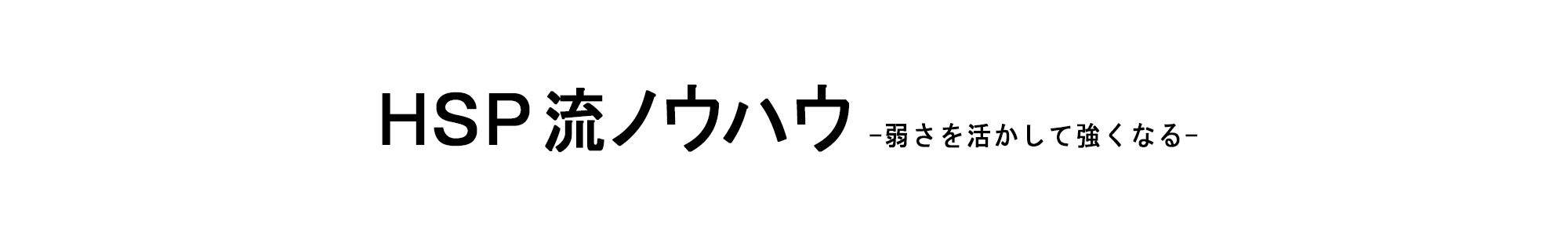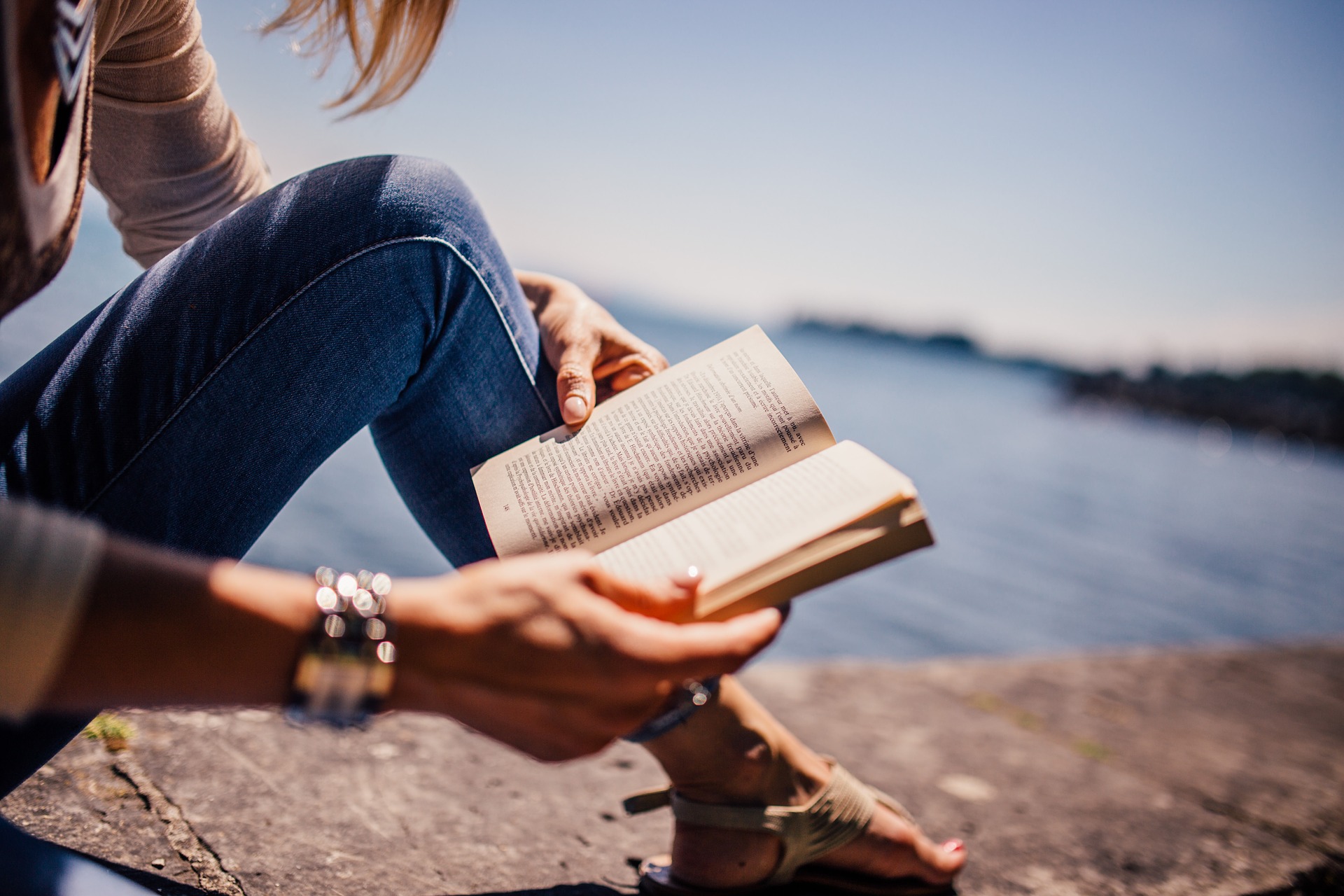外向的な人間であるほうが社会的には良いとされてきましたが、最近では「内向型人間」に注目が集まっています。しかし、まだまだ社会は外向的な人向けに作られた学校・組織が多くあります。では、外向型と内向型の違いというのはどういう所でしょうか?基本的な違いと、両者が共存しあう方法について考えてみました。
遺伝の影響が40~50%
内向的か外向的になるかは、40~50%が遺伝によって決まります。アジア圏には内向型が多く、ヨーロッパ圏には外向型が多く分布しています。
半分は後天的な要素を含みますが、生まれ持った遺伝子は変わりません。特に内向的な性格は社会に理解されづらく、自分に対して否定的に受け取るクセができやすい。
自分の特性を受け入れ、内向型の強みを活かしていくのが良いでしょう。
刺激に対する反応の違い

ジェローム・ケーガン氏による実験で、生後4カ月の乳児に様々な刺激を与え反応を観察した。
20%:「高反応」その際に手足をばたつかせたり、元気よく泣いた
40%:「低反応」静かに落ち着いていた
40%:「中間」高反応と低反応の間
内向的になるのは、手足を元気よく動かした「高反応」グループであり、落ち着いていた「低反応」グループは外向的になるとケーガン氏は予想した。その後、その乳児たちを2歳、4歳、11歳の時点で研究室に呼び、観察したところ、予測どおりだったと発表された。

高反応を示した20%の人たちについて、エレイン・アーロン氏は「HSP(Highly Sensitive Person)」という概念を提唱しています。HSPは“とても敏感な人””とても繊細な人”という意味で、HSPのうち内向型70%、外向型30%であると言われています。後天的な影響によるものなのか、必ずしも高反応=内向的になる訳ではないようです。
丁度いい刺激レベルが違う
内向型の良い刺激レベル
- 親しい友人とほどほどに遊ぶ
- 読書
- 美術品鑑賞 など
弱めの刺激が内向的な人にとっては”ちょうど良い刺激”になります。
外向型の良い刺激レベル
- 初対面の人に会う
- 急斜面でスキー
- 大音量で音楽を聴く など
強めの刺激が外向的な人にとっては”楽しめる良い刺激”になります。
両者が最適な刺激レベルに
外向的な人と内向的な人が共存し合うためには、お互いの最適な刺激レベルが違うことを認識して尊重し合うことが大切です。
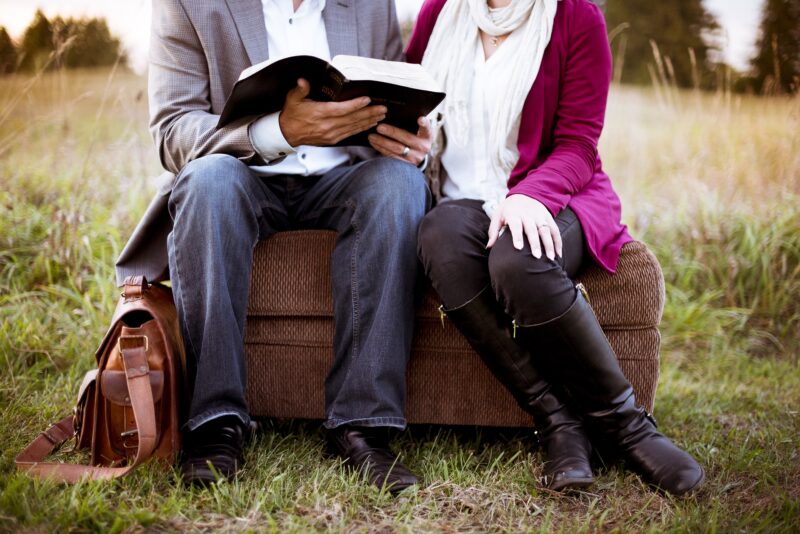
外向型の刺激に合わせてもらうなら、内向的な人が静かな場所・人の少ない場所で休憩できる時間を設けること。
内向型の刺激に合わせてもらうなら、内向的な人は自分が饒舌になるような場所・話題にすること。外向的な人は弱い刺激に飽きてしまうので、飽きさせない話し方を身に付けておくと良い。

例えばそれが家族だった場合…親が内向的な子供の性質を受け入れられず、多くの人と関わらせようとしたり、内向的であることをネガティブに捉えてしまう。子供であっても友人や恋人と同じように尊重し、内向性を活かせる方法・場所を見つけてください。
子供の場合は、刺激を与えるときに段階を踏んで、こまめに子供の気持ちを確認することが大切です。
親が外向的な場合、子供が“言ってこないから聞かない”という行動を取りがちです。最初からうまく出来なくても良いので、声を掛けて聞こうとしてみてください。親子で交換日記をしてみるのも良いでしょう。
【まとめ】内向的な人の特徴

一人もしくは少人数が好き
限られた相手にエネルギーを注ぎたいと考えているので少人数との関係性を重視します。一人になることでエネルギーを充電するので、親しい相手であっても一緒に居続けるのは苦手です。
内向型は「調べること」外向型は「反応すること」に特化しています。
考えてから話す、行動する
無駄な話を長く続けるのが苦手で、深い内容の対話を楽しみます。会話より書くほうが自分をうまく表現しやすいを感じる人も多いです。
”とりあえず”で行動するのが苦手なので、頼みごとは要点をまとめてからにするとスムーズに動いてくれます。
内向型は脳の抑制システムが活性的
抑制システムがよく働いているので、物事をよく考え本質を見ます。
お金や名声、ブランドなどの表面的なものに惹かれにくく、自分の内面に重点を置きます。
失敗や間違った行動をしたら、なぜ失敗したのか?を考えるので同じミスを繰り返しづらいです。

うるさい場所や刺激が苦手
刺激に反応しやすいため、人の多い場所や賑やかな場所は苦手。図書館や水族館、美術館や演劇鑑賞などが心地よいと感じる。
求める友人のタイプ
謙虚、利他的、正直、勤勉な相手をよき相手として評価し交友関係を結ぶ傾向にあります。
内向型の著名人
ウォーレン・バフェット、アルバート・アインシュタイン、マハトーマ・ガンジーなど
【まとめ】外向的な人の特徴
一人より大人数が好き
孤独が苦手で、仲間を強く求めます。社会で活動することでエネルギーを充電します。初対面の相手と話すのが苦にならず、人と会った後でも気疲れしないので元気なままです。
考えずに、まず反応する
外向型は「反応する」ことに特化した性質があるので、考えずそのまま口に出します。積極的で、自分が主導的な会話を好むので相手の話を聞くより自分が喋ることが多いです。
思っていないことを衝動的に口にしてしまう傾向があります。
外向型はドーパミンが活性的
ドーパミンの放出量が多かったり、報酬システムが過敏に受け取るようになっているので報酬(熱狂)を求めます。
権力やお金など様々な報酬を求めるので、内向型よりも多くの喜びを体験する傾向があります。

単調なことに飽きやすい
刺激に反応しにくいため、静かな場所や単調な作業には飽きてしまいます。旅行やライブ、激しいスポーツなどを楽しいと感じる。
求める友人のタイプ
楽しく、活動的、社交的な相手をよき相手として評価し交友関係を結ぶ傾向にあります。
外向型の注意
外向的な人の中でも、特に衝動性の高い人については破滅傾向が高いので注意が必要です。
衝動性の高い人は目標達成に集中しすぎるあまり、間違った行動を取ったあとに次の決断までの時間を短くしてしまいます。
その結果なぜ失敗したのか?を考えず、人に相談をしなかったり、相談してもアドバイスを受け取らないので、より悪い状況に陥ってしまうことがあるようです。
そういった際には「ペースをゆるめる」ことが必要です。

多くの人が両向型
100%どちらかという人はまず居ません。大半が「両向型」というどちらの性質も持っています。外向性と内向性のどちらの方が高いかを調べるならば、インスタントビッグ5で性格分析をしてみると良いかもしれません。
しかし、外向型と内向型の共存についてひとつ思うところは、外向型の人がこの記事を読むことが少ないだろうという点です。高い刺激を求める故に、読書などの刺激が弱いものに対して消極的であり、人との関わりの中で知識や経験を得ていきます。学び方の違いから生まれる齟齬が、両者を理解し合えなくしている点ではないかと考え悲しく感じています。
参考文献
youtubelスーザン・ケイン 「内向的な人が秘めている力」
The GuardianlHow extroverts are taking the top jobs – and what introverts can do about it
Amazonl「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる 「繊細さん」の本
Amazonl内向型人間の時代 社会を変える静かな人の力
Amazonl内向型のままでも成功できる仕事術
Amazonl内向型人間だからうまくいく (祥伝社新書)