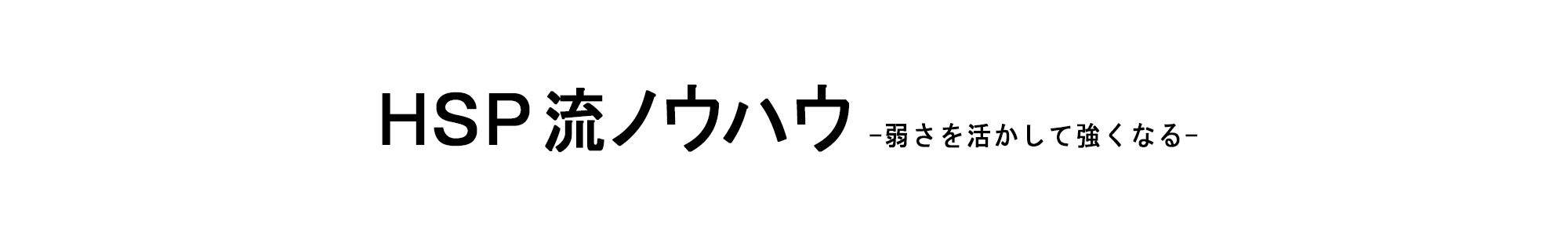HSPとは―― Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)
HSPはHighly Sensitive Person(ハイリー センシティブ パーソン)の略で、アメリカの心理学者エレイン・N・アーロン博士が提唱しました。
“とても敏感な人””とても繊細な人”という意味で、5人に1人の割合(全人口の15~20%)でいるとされています。また、他の動物にも同じように刺激に反応しやすい固体が同じ割合でいると言われています。
HSPを表す指標「DOES(ダズ)」
①Depth of processing(思考の深さ)
…想像力が豊かで、熱心に研究するのが得意な傾向にあります。内省的、思索的な傾向が強く、表面的な世間話などは不得意です。行動に移すまでに考える時間が長く、引っ込み思案な面もあります。
②Overstimulated(神経の興奮しやすさ)
…その場にいる人の感情やその場の雰囲気、光や音などを人一倍強く感じます。恐怖感を覚えやすく、他者の不機嫌さなど小さなことにも緊張して疲れてしまいます。また楽しいことも疲労に繋がるため、気づかぬうちにダメージが溜まっていることがあります。
③Emotional reactivity and high Empathy(感情移入、共感性の高さ)
…本や映画のストーリー、芸術作品や風景などに深く感動することができます。人の思いに細かく気を配り、ときに気を使いすぎて疲労してしまうことも。友人の相談に乗って自分まで涙する、同僚が叱られている傍で本人よりダメージを受けるなど、他者の経験を自分のことのように感じます。
④Sensitivity to Subtle stimuli(五感の鋭さ)
…人混みや散らかった空間など、視覚情報が多すぎると疲れてしまいます。大きな音、複数の音が混じった状態を苦手とする傾向があります。冷蔵庫の音や時計の針の音が気になる人も。感触や温度・痛みなどにも敏感なので布地のチクチク感、強い匂い、カフェイン刺激、食品添加物などの刺激も受けやすいです。総じて感受性が鋭いため、芸術を深く味わえるプラス面もあります。

これらは生まれつきの気質であり、病気ではないため医学の概念には含まれていません。そのため、HSPかどうかを病院で判断することは難しく、自分の気質とどう付き合っていくかは自身で理解を深めていくほかありません。
タイプ別HSP
内向型HSP…HSPのうち7割が内向的な性格といわれています。内向型は自分の中からエネルギーを得られるタイプで、残り3割の外向型は社会的環境からエネルギーを得られるタイプに分けることができます。
外向型HSP…細かいことに気付いて相手を思いやることが得意なHSPの気質を持ちながら、社交的でリーダー向きなタイプです。刺激を求めますが、刺激に疲れやすいという相反する性質を持っています。
HSPと非HSPの違い

HSPと非HSPの大きな違いは、脳の神経システムにあります。HSPの人は赤ん坊の頃から刺激に反応しやすく、同じストレスに晒されたときに、神経の興奮に関わる物質やストレスホルモンといわれるコルチゾールが多く分泌されているようです。
また、HSPの人はミラーニューロンなどの共感に関わる脳システムが非HSPより発達していると言われています(現在はまだ検査数が少なくハッキリしていません)。ミラーニューロンは「物まね細胞」とも呼ばれ、他者の行動を見たときに自分が行動しているかのような反応をする脳神経細胞のことです。相手の悲しみや喜びを自分ごとのように感じられるのは、ミラーニューロンの反応によるところが大きいです。
HSPの特徴

- 長時間、人といると疲れてしまう
- 電車や会社など、攻撃的な人がいると気が重くなる
- 大人数が集まる会議やパーティーなどが苦手
- 人との境界線がうすい
- 過去、現在、未来の境界線もうすい(昔のことをグルグル考えてしまう)
- 人に頼るのが苦手
- 誰かに見られていると緊張してやりづらい
- 強い光、大きな音が苦手
- 想像力が豊か
- 自分を責め過ぎてしまう
- 頑張りすぎてしまう
HSPのより詳しい記事はこちら→HSPの特徴。
子供のHSP(HSC)とは?
HSPは主に大人に対しての名称で、子供の場合はHSC―Highly Sensitive Child(ハイリー・センシティブ・チャイルド)と呼ばれます。子供のころは、まだ自分の隠された能力に気づけず自分を卑下しがちな傾向があります。苦手なものは大人(HSP)の場合と同じですが、家族からの理解が無い場合はより傷つきやすい性質になります。
HSCの親は
- 大声や感情的に怒らない
- 子供を責めたり、人と比べる言葉は避ける
- 子供が息苦しさを感じていても否定しない(”おかしい”や”気のせい”などの否定表現)
- 誰とでも仲良くさせようとしない(大人であっても、全ての人から好かれる事は無理)
- 甘えや努力で治せるものではないと理解する(人それぞれに身長が違うのと同じ)
- フィクション系の本を読む機会や、美術館・映画館などに訪れる機会を増やす
HSCの特性を理解し、柔軟な発想を持つことで子供から得られることも増えていきます。
HSPが合わない人(絶対避けるべき人)
- 愚痴の多い人――可哀想な人であり続ける事(承認欲求を満たすこと)が目的なので、アドバイスをしても実践をしない。
- 攻撃的な人――HSPが好感を持てない人なので、無理に好きになろうとしなくて良い。
- 支配的な人――不安や罪悪感をあおってくる。支配(自分の存在を示すこと)が目的なので、人への共感力が乏しい。
自分の中でモヤモヤする人とは、物理的に距離を取るようにして共感性をシャットアウトしましょう。
HSPと合う人
- 精神的に安定していて、トラブルにも動揺しにくい人――マイナスの影響を受けにくいので、HSPが安定した生活を送りやすい。怒りや不満の感情が出やすい人だと、影響されて精神不安定になりやすくなる。
- HSPの敏感さにいちいち反応しない人――冷静さの影響を受けられるので、焦っているときに落ち着きを取り戻しやすくさせてくれる。同じように反応する相手は、HSPが負のスパイラルに陥る。また、機嫌と取ろうとして一人させてくれない相手もより疲れる。
- よく傾聴できる人、読解力や理解力のある人――HSPの熟考する特性を尊重して話し合いができるので、お互いを尊敬・理解し合える。その反対に、一方的に話す人や噛み砕いた説明をしても理解ができないタイプはストレスが溜まりやすい。
HSPは、人から良い影響も悪い影響も受ける性質です。であれば、関わる人を選び良い影響与えてくれる人との時間を増やすようにしてみましょう。

まとめ
HSPの特性は周りから「気にしすぎ」「メンタルが弱い」などと言われ、職場や家庭で生きづらさを感じやすく、自尊心の低い考え方になってしまいがちです。しかし、生物の生存戦略において危機を察知する力に優れた種が、必要であったからこそ今でもHSPのような性質は残っているのだと思います。自分の気質について正しい理解をすることで、その特性を活かし誰よりも楽しく生きられるのがHSPの強みでもあります。去年より今年、5年前より今の自分が過ごしやすくなる環境を整えていきましょう。
参考文献
amazonl「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる 「繊細さん」の本
amazonl繊細な人が快適に暮らすための習慣 医者が教えるHSP対策
amazonl「敏感すぎて苦しい」がたちまち解決する本